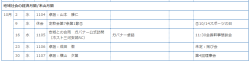第1106回 例会 2024年10月23日(水)
更新日:2024/10/23
第1106回 例会
ビジターならびに、ゲスト:おみえになりません
本日の卓話担当:矢田良一さん
1.点鐘
2.ロータリーソング斉唱(第3週)、4つのテスト唱和
3.弥政晋輔会長 挨拶
皆さん、こんにちは。
今日は予定が立て込んでおりますので、短めにご挨拶申し上げます。
最近テレビを見ていて、画面中央にテロップが出てくることが多いことに気付かれていらっしゃるでしょうか?
数ヶ月前ほど前から、どこの民間放送、NHKも横並びで始めています。
特にニュース番組は同時入力なので誤字脱字が多いですという注意書きをしながら流しています。
タイムラグが10秒ほどありますので、画面と違う約10秒前のテロップが流れていて違和感を覚えることが多々あります。
そういうことを感じている方がいらっしゃいますでしょうか?
お仲間がいるようでうれしいです。
以上です。
5.杉浦秀郎幹事 報告
(1)次週例会終了後、定例の理事会を開催について
(2)ロータリー希望の風奨学金を送金しましたことをご報告いたします
(3)他クラブの例会変更を事務局に確認の上、メーキャップの方お願いいたします
7.植村律保さんを偲んで
〇ご挨拶 (植村真一さん)
本日は亡き父、律保を偲ぶ会を開催していただき、誠にありがとうございます。
また、通夜・葬儀には多くの方がご多用の中参列していただき、誠にありがとうございました。
温かいお言葉、励ましのお言葉を多くいただき、父も喜んでいると思いますし、私自身としても励みになりました。
父の思い出の写真を見ていると、JCやロータリーの写真が多く見られました。
仕事ではない場所で、このような時間を作っていただき、父も感謝していることと思います。
まだまだ若輩者ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします。
〇神谷 宏さんより植村さんとの想い出
植村さんがお亡くなりになったその日は、大変ショックを受けました。
植村さんは何度も大きな病気になられましたが、いずれも元気に戻ってこられていたので、不死身だと思っておりました。
残念でなりません。
まだよもやま話などする機会があると思っていただけに、とても残念です。
植村さんとはJCからご指導いただいておりました。
ロータリーに入会してからも、何かと気にかけていただいておりました。
個人的には鯛を釣りに二人で行ったことがございます。
前夜から泊り、知多半島の先端に行って鯛釣りをするのですが、その豪快で滅多にかかることのない釣りで、私はビキナーズラックで釣ることを経験で木、その後も誘っていただきました。
また、ゴルフでは暗いうちからコースに出かけたり、色々と貴重な
経験させていただきました。
植村さんは人の好い所だけを見て、褒める方でした。
私も日頃から見習いたいと思っているのですが、なかなか難しいことで、得難いことです。
言葉遣いも丁寧で、大変な紳士で人生のお手本でした。
〇寺部保美さんより植村さんとの想い出
事の始まりは、ある方をロータリーに勧誘しようということになり、一緒に出掛け、その日の夕食を共にしました。
それから何故か毎週お食事のお誘いがあり、何故かある日から一緒に生活するようになりました。
山本雅仁さんがゴルフに行く時にお迎え来てくれた時には、これまた何故か「隠れていろ」と律様は仰られました。
八千代病院に入院した際には、私は毎日寝泊りをしました。
そして、毎朝弥政先生が顔を見に来てくれました。
後日、弥政先生は「ロータリーの友情はすごい」と思われたそうです。
・・・友情でここまでするわけはないですよね。
食道楽の律様は、夏は鮎や伊勢志摩の牡蠣を、秋には恵那のマツタケを、冬には越前まで蟹を食べに行きました。
大晦日・元旦は、西浦温泉の銀波荘に行くのが年中行事でした。
そこで元旦のご来光を仰いで、新しい気持ちで新年を迎えました。
元気な時は、時折会社に参り、ゴルフを楽しんでおりました。
土日には、現場の職人さん達にちょっとしたおやつを差し入れに行くのが習慣になっておりました。
夜には、律様の足を揉むのが日課でした。
彼は「この時が一番幸せだ」と言ってくれました。
今日まで喧嘩することなく穏やかに過ごせました。
沢山の素晴らしい想い出を与えてくださり、今の私の力となっております。
そして、喪主を務められた真一さんの「立ち止まるわけにはいかない」という言葉に勇気をもらっております。
これからは律様に恥じないようにしっかりと自分らしく生きてまいります。
素晴らしい第2の人生をくださった律様、ありがとうございます。
それから、今日まで律様に心温かく気遣いをしてくださいました皆様に心より感謝し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
10月8日、植村律保さんのお通夜にお参りさせていただきました。
少し早めに着きましたので、棺の中の律保さんをお参りすることが出来ました。
神谷 宏さんも仰られていましたが、植村律保さんという方は本当に紳士な方でした。
私にも気軽に話に乗ってくれ、ほとんど私が話しかける方でしたけど、本当に驕ることなく話を聞いてくれました。
そんな植村さんは、棺の中でも本当に紳士的で、大変驚きました。
こういう人生もあるのかなと感じました。
6年か7年ぐらい前に、事務所で棺プロジェクトという企画をしました。
棺と言っても段ボールで出来ておりまして、それがまたとても頑丈なものなのです。
上に人が乗っても大丈夫というような棺です。
それを置いて、もし希望があればその中に入ってもらい、蓋をして、暗闇の中で3分物思いに沈んでもらう。
そんな体験をしてもらおうと思い企画したのですが、私以外皆絶対反対だということでボツになってしまったいました。
あの事務所に行くと、棺が用意してあって棺に入れられちゃうぞと、そんな噂が立ったら絶対困るなというのもあったので、その当時は諦めました。
しかし、その体験というのはとても大事だなと思うのです。
実は、それを実践している方がおられます。
中村仁一氏という『大往生したけりゃ医療とかかわるな』というベストセラーの本の著者です。
中村氏は関西の高雄病院の院長・理事長を経て、著作もあり、仏教の勉強もずいぶんされていたようです。
このスライドは棺の中の自分です。
棺桶に入るというのは、私の考えでは人生のいずれ必ずそこに入るわけです。
終着点から自分の人生今の自分を見つめると、そういうことが体験できるわけです。
色々な本を読むと、それを実際に実践している方の感想が二つにわかれるそうです。
「まだやりたいこともあるし、行きたいところもある。こんなものどうもならん」
という否定的な感想と、
「いずれここに入るというのなら、心の準備をしていかないといけないな」
という肯定的な感想です。
棺桶に入って、問います。
「自分はこの先何が出来るのか」
私も60歳になった時に再開したいことがありました。
20代の頃に山歩きを覚えて色々な所に行きましたが、あの頃はお金が乏しくて高い登山靴が買えませんでした。
60歳になったら再びやろうと思って、あの頃買えなかった登山靴を買いました。
しかし、60歳の誕生日を過ぎてすぐ、八千代病院に運ばれました。
第5腰椎分離症という治らないものに罹り、あんなにやってやろうとも思っていたことが結局できなくなってしまいました。
そのような非常に辛い思い出があり、この先何ができるかという発想はやはりとても大事かなと思いました。
その思いから棺桶に入ってもらおうという企画を思いついたわけです。
皆さんは肯定派でしょうか。それとも否定派でしょうか。
【今、なぜ、エンディングノートなのか】
今なぜエンディングノートなのか。これってこのオイルっていうことを、私が考えるの考えるようになったのは40歳ぐらいです。
ちょうど平成バブルがはじけて、平成4年に事務所を移して始めました。
しかし、やはり時間が空いてしまう時期があり、何かお役に立ちたいし勉強もしたいなと思い、公民館で高齢者教室を始めました。
基本的なテーマは
「老いること」
これをどういうふうに受け止めるか。
去年出来ていたことが、今年出来なくなる。
先月出来ていたことが、今月出来なくなる。
昨日で来ていたような気がする、今日は調子が悪いなど。
そういう、できることが失われて失われていく日をどう受け止めていくのか。失っていく日々だが、できることが必ず残されているということなのです。
人生を山の形に例えます。
人生のピークに向かい登っていく中で、70歳を迎えるころにはピークの頃と比べて60%くらい出来なくなってしまうのです。
この出来なくなってしまったことに目を向けて嘆くのではなく、残ったことで何ができるか、そちらの方に注意を向けるしかないと私は考えます。
出来ることに目を向けて、その先を描くことで小さなことが沢山叶っていくのではないでしょうか。
【エンディングノートを埋めていくことは勇気が必要】
自分の人生の終末期と真正面から向き合うというのは勇気が必要です。
そして、向き合うことは人生にとって大切なものは何かが明らかになっていく。営みであります。
このノートの目指すところは、終末点から自分の人生を見つめて、これからあと何ができるかという考えを描いていくということです。
もう一つは、本当に大事なことは次の世代に伝えていきたいということです、
この二つが私が作ったエンディングノートの趣旨です。
【エンディングノートを書くメリット】
(1) 家族のため
亡くなった時、本当にまだ元気だと思われている方が亡くなってしまったら、心の準備って本当に大変なことです。
色々なことを準備しておけば一番家族が助かると思います。
また、自分自身も準備しておけば叶うことが必ずあるということです。
(2) 安心するため
将来に備えることで、今を安心して過ごすことができます。
準備がしてあると、心の安定さが培われるのではないかと思います。
「いつ死んでもいいぞ」という心の準備がしてある人の方が安心して長生きと思います。
(3) 書くことで頭の中が整理できる
文章にすると、思考が深まって色々な事が整理できます。
今はスマホの時代ですから、スマホでも思っていることを文章にして後から見返してみるのも良いのではないかと思います。
(4) 終活をスタートするきっかけとなる
いかに相続がうまく収まるかということを、自分の終末期の生活も含めて対策することが出来ます。
(5) 家族でコミュニケーションできる
日本人はお金のことを話すのが苦手な性質でもありますから、それをきっかけに話すことが出来るでしょう。
~その後の項目は割愛~
【楽しかったことを書き出す】
楽しかったことをいくつか書き出してみましょう
私の母も、晩年は本当に愚痴が多かったです。
何故多かったのかというと、楽しかったことを忘れてしまっているからなのです。
どんな小さなことでも楽しかったことを書いておけば、そのことを思い出すことが出来ます。
自分の人生を長く振り返ることができる手法になるので、これを入れてあります。
今日は時間の都合上「前編」とさせていただきます。
ありがとうございました。